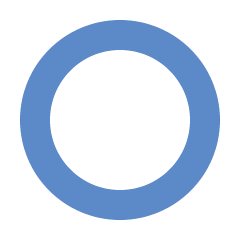総合病院における電気痙攣療法
Electroconvulsive Therapy in the General Hospital
電気痙攣療法とは
薬剤治療抵抗性のうつ病患者や治療薬の副作用に耐えられない患者が多いため、電気痙攣療法は総合病院において未だに必要不可欠な治療法である。抗うつ薬に関する大規模臨床試験では、67%の患者しか完治に至らず、残りは非反応性または部分寛解にしか至らない。一方で、電気痙攣療法に関しては、70−90 %の改善率があると報告されている。うつ病は、心血管イベントの罹患率や自殺との関連が強く、有効な治療が求められている。さらに、国際的にみても、罹患者数は全疾患中第4位に位置しており、2020 年には2位まで浮上すると予想されている。現状では、ECT はうつ病の有効的な治療に対するニーズに最も応えうる治療法であると言える。
電気痙攣療法の適応
ECTへの良好な反応性を予測させる大うつ病の症状は、食欲不振、体重減少、早朝覚醒、集中力欠如、厭世気分、落ち着きのなさ、会話の遅さ、便秘、心気・罪業妄想である。最重要な症状は、以前は楽しめた活動に対する興味の喪失である。これらはまさに、抗うつ薬の適応と同じである。現在のところ、抗うつ薬への抵抗性を予測する方法はない。最近は薬物治療抵抗性のうつ病に対しての多少の共通見解はあり、薬物治療失敗の判断は前の治療の妥当性によって変わる。また併存疾患もこれに影響する。若く、健康で、希死念慮のない患者はECTに移行する前に、4種類以上の薬剤を安全に使用できるだろう。一方で、高齢のうつ病患者は、一種類の薬剤にも耐えられず重篤な予後をたどる可能性がある。
他の要素もまた。薬物治療からECTへ移行する要素となる。希死念慮は薬物治療からECTへの早期移行適応であり、80%がECTで改善する。
精神分裂病はECTの第2の適応疾患である。統合失調症の標準治療ではないが、抗精神病薬の併用により、薬物治療抵抗性の慢性統合失調症の80%に持続的な改善がみられる。加えて、最近は、統合失調症または統合失調感情のある患者にECTとクロザピンの短期投与を併用することの安全性が報告されている。統合失調様障害の典型的な症状(急性発症、感情障害なし、感情障害の家族歴がある)を満たす若年の精神病の亜型群は、慢性統合失調症よりもECTへの反応性がよく、しばしば完全寛解する。
躁病にもECTが著効することはよく知られているが、薬物治療が第一選択である。しかし、対照研究でECTがリチウムと同等(またはそれ以上)の効果があり、薬物治療抵抗性の躁病の50%がECTによって改善することが示された。最近の研究ではこれらの病気にはECT は効果的かつ安全だがまだ十分に活用れていないことがわかった。予備的な研究では、ECTが成人の難治性双極性障害を安定化させるという結果も示されている。患者のほとんどには、その診断に関係なくまず薬剤投与が試されるが、以下の患者にはECTが第一選択になる。
1. 深刻な栄養不良や、脱水、疲弊した患者。遷延したうつ病に伴うこのような患者は医学的に危険な状態にあり、慎重な水分補正の後に直ちにECTを開始すべきである。
2. 内科疾患(例:不整脈、冠動脈疾患) がある患者。このような患者ではしばしばECTの方が抗うつ剤よりも安全に治療できる。
3. 妄想性うつ病の患者。多くの王創生うつ病の患者は抗うつ剤単独では改善しないが、ECTによる妄想性うつ病の改善率は80−90%に及ぶと報告されている。
4. 以前の薬物治療に反応しなかった患者。
5. 緊張病の患者。大多数の緊張病患者ではECT が即効性を示す。
緊張病症候群は感情障害と関連する場合が最も多いが、統合失調症や代謝性疾患、種々の脳内病変、SLEの症状の場合もある。治療されなかった緊張病の死亡率は50%にも及びこと、また、致死的でない合併症(肺炎、静脈血栓、四肢拘縮、褥瘡を含む)も重篤となるという理由で、迅速な治療が必要である。原疾患に関わらず、ECTの有効率は75%に及び、多くの緊張病患者の治療として選択される。ロラゼパムも緊張病に対して短期治療薬としては有効だが、長期的な効果は確認されていない。悪性症候群は、高熱、後弓反張、筋硬直が緊張病よりも多いが、臨床的には緊張病と鑑別しにくいことがある。
50例以上の症例報告で、薬物治療が奏功しなかった悪性症候群にECTが有効であったという報告があるが、集中的な内科治療、抗精神病薬の中断、ダントロレン、ブロモクリプチンの使用が基本となる。
いくつかの症例報告はECTが認知症に関連した行動障害、攻撃性、病的な絶叫(薬物の治療には反応しないとされていた)に効果的であるする。ECT による認知障害のリスクもなるため、これらの認知症患者のECT適応については事前に慎重に議論すべきである。認知症の合併がある抑うつ患者はECT後にとりわけ重篤な認知障害をおこしやすい;幸いにも、ほとんどの患者が治療後に治療前のレベルまで戻るか、または改善する。同様に、ECT はその他無数の状態の治療として有効である。パーキンソン病(精神病の合併の有無に関わらない) の運動症状にも効果的という報告もある。加えて、ECT は中毒や代謝性脳症によるせん妄や難治性疼痛( 神経疼痛、線維筋痛症、複合性局所疼痛症候群など) のコントロールにもECTは効果的である。
有害事象につながる危険因子
ECT の管理技術が進歩したことで、以前は絶対禁忌であった症例が相対的危険因子となってきた。治療のリスクとうつ病が続くことによる致死性を天秤にかけながら、方針を決定することが、患者にとっては最も有益である。一般に、ECT の絶対的禁忌はないとされているが、いくつかの状況では慎重な精査や管理が必要となる。
ECT 下では、心臓に生理学的な負担がかかる。発作が始まると同時に心臓活動が急激に増加するが、これは初めに間脳からの交感神経系の興奮伝達が、脊髄交感神経経路を介して心臓に働くからである。この興奮伝達は発作の間続き、血中カテコラミン濃度の上昇に伴って増大し、3分後にピークに達する。発作終了直後は服交感神経系が優位になり、しばしば一過性の徐脈や低血圧の原因となるが、5~10分後には元に戻る。
この自律神経系の刺激によって増悪する心臓の病態で、最もよく見られるものは虚血性心疾患、高血圧、うっ血性心不全、不整脈である。これらの状態も、適切な管理をすればECT に耐えることができる。心電図上でのQT 間隔は、ECT 中の不整脈の出現を予測するのに有用である。心筋梗塞を発症してから6ヶ月以内での全身麻酔は禁忌であるという考え方は一般的であるが、原著のデータの曖昧さを考慮すると驚きである。ECT 中に増加する心活動に必要な心臓の予備能を慎重に評価した、より合理的な研究が報告されている。動脈瘤は可能であればECT 前に治療しておくべきであるが、頭蓋内動脈瘤や大動脈瘤のような血圧管理の重要性が強調される状況下でも、安全にECT を施行したという30以上の症例報告がある。また中等度から重度の大動脈狭窄や残存左室機能の患者に対しても安全にECT を行えたという報告があるが、可能であるなら、重症の大動脈狭窄は一連のECT 治療前に外科的治療を行うことが望ましい(発作中の心負荷を避けるために)。ペースメーカー患者はECT に支障なく耐えることができると知られているが、全てのデバイスの適切な動作、患者のストレッチャーの断熱性、刺激中は誰も患者に触れないことを徹底するなど、事前の準備は必要である。また磁石は使用可能であるか、徐脈になる可能性はあるか、ペースメーカーのモードを変換する必要があるかなども含めて。埋め込み型除細動器をつけている患者には、安全に心拍を監視するため、そして外部の除細動器の使用を可能にするために、ECT 中は電源をオフにすることが最近では勧められている。うっ血性心不全の患者はECT に耐えられるが、左室駆出率が20%以下の患者では一過性の代償不全から5~10分間の肺浮腫になることがある。この原因が、神経を介しての肺への刺激によるものか、心拍数と血圧が上昇し心拍出量が減少することによるものかは明らかではない。高血圧患者と非高血圧患者において、ECT 前後の血圧に関する後方視的研究では、ECT 治療で、治療時間の長さに関わらず、高血圧患者の血圧が悪化することはなかった。
脳もまたECT 中に生理学的に負荷を受ける。脳酸素消費量は2倍となり、脳血流量は数倍に上昇する。頭蓋内圧は上昇し、血液脳関門の透過性は亢進する。これらの急激な変化によって、種々の神経疾患を伴う患者において、ECTの危険性が上昇する。
数年前には、占拠性脳病変はECT の絶対的禁忌とされていたが、それは脳腫瘍患者にECT を施行し、症状が悪化したという症例報告があったからである。現在、一般的な意見は、占拠病変が比較的小さくて、独立しており、重大な腫瘍の影響、脳浮腫、頭蓋内圧上昇と関連がなければ、その他の治療と比較してECT が神経学的により悪化させるということはない。しかしながら、腫瘍が大きい、複数である、脳浮腫、頭蓋内圧上昇などがあれば、ECT は相対的禁忌と考えるべきである。そしてもし治療を受けるのであれば、脳浮腫の軽減や、頭蓋内圧上昇を減らすための対策をとるべきである。おそらく脳梗塞が、最もよく見られる脳内の危険因子である。脳梗塞発症直後の患者に対してECT を行った症例報告では、適切な治療が行われていれば、合併症の発生率は低いものであった。このためECT は、しばしば脳梗塞後の抑うつの治療として行われる。脳梗塞発症からECT 施行までの間隔は、うつ病治療の緊急性によって決めるべきである。
ECT は水頭症、動静脈奇形、脳出血、多発性硬化症、SLE 、ハンチントン舞踏病、精神発達遅滞に対して安全に施行でき、効果的な治療法である。またECT は喘息患者にも安全に行われる。最近のガイドラインでは、ECT の当日の朝に吸入を行うことを推奨している。しかし、テオフィリン投与中の患者にECT を施行する場合は注意が必要である。なぜなら、この薬剤は発作を延長し、てんかん重積に関係するからである。
重篤なうつ状態となった妊婦では、低栄養や自殺を防ぐためにECT が必要である。限られたデータでは、ECT は妊娠中の重篤な精神疾患に対して効果的であり、胎児や母体へのリスクは低いと示されている。妊娠中のECT の準備として、骨盤の計測、必要でない抗コリン作用薬の中止、陣痛測定、輸液、胃薬の投薬である。ECT 中は母体の右骨盤を挙上し、胎児の心拍モニタリングを行い、過剰な過換気を避けることが推奨されている。胎児は母体の間脳との直接の連絡がないために生理学的な負荷から守られており、けいれん発作中における母体の自律神経末端臓器からの集中的な自律神経刺激は免れている。
最後に、サクシニルコリンのような脱分極性の筋弛緩薬は、特定の病状の患者では副作用を起こすかもしれない。そのような状況下では、替わりに非脱分極性の筋弛緩薬を使用することが良い。バルビツール系は、ポルフィリン症の患者には安全ではないので、代わりの麻酔薬を使用するべきである。
方法
ECT の術前評価には、詳細な既往歴と身体所見が含まれる。胸部X線写真、心電図、尿検査、血算、血糖値、尿素窒素、電解質なども測定する。加えて、必要であれば追加の検査も行う。認知障害のある患者では、うつ病そのものが認知障害の原因となるため、中枢神経系の病変の検索が必要となるかどうかの判断が困難なことがある。代謝機能スクリーニング、CT 、MRI は、しばしばうつ病以外による認知障害の原因の除外に有用である。痴呆が原疾患であるかどうかについて疑問がある場合には、神経内科医による診察が必要になる。神経心理学的検査は、痴呆と仮性痴呆の診断には有用ではない。
ECT を開始する前に、患者の全身状態を最適にしておくことが必要である。高齢患者は入院時、極度の低栄養や脱水を呈している。このようなときは、脱水が改善されるまで、ECT を数日間延期するべきである。必要であれば経管栄養も用いる。もし患者がジギタリスを使用しているなら、中~低濃度の治療域にするべきである。降圧剤はECT 前に最高量にしておき、ECT 中の反応性の高血圧を予防する。多くの糖尿病患者は、ECT が終了するまで、朝のインスリン投与量を一定にしておくと、糖尿病がより安定する。糖尿病患者はうつ病が改善するにつれて、インスリンの必要量は減少するため、ECT 治療期間中は血糖値を頻回に測定する必要がある。
抗精神病薬とECT を同時に行うかという問題は、いくつかの推論が行われており、研究が行われている最中である。一般的に、十分な投与量と期間の治療を受けているにもかかわらず利益がないのであれば、投薬は中止するべきである。以前の研究では、リチウムを内服している患者は、ECT を受けると、重篤な認知障害や、覚醒や呼吸までの時間の延長や、自発けいれんの延長などが起こるとされていたが、しかしさらに最近の研究では、特定の病状の患者では、併用することは安全で最適な効果があると示している。すでにリチウムを投与されている双極性障害の患者に対して、臨床医は、リチウムを突然中止すると躁病の危険があり、ECT を行う前に洗い出しがあるので治療を延期することを考慮するべきである。ベンゾジアゼピン系薬物もまた、けいれん発作に対して抑制的に働くため、中止するべきである。鎮静のために、ECT を受ける前の患者はフェノチアジン系薬剤(ペルフェナジン4~8mgを6時間毎)や非ベンゾジアゼピン系薬剤(ヒドロキシジン50~100mgを1日2回、ジフェンヒドラミン25~50mgを1日2回)の投与を受ける。三環系抗うつ剤は、術中の心血管系の管理をより困難にさせるため、術前に中止するべきである。MAO 阻害薬とECTの間には、けいれん発作を減弱する作用と、麻酔薬との間に相互作用があるので、原則的には使用を控えるが、ECT 前の10日間の洗い出しは必要ない。けいれんの既往のある患者では、強度の電気刺激によってのみ、けいれんが生じやすくなるように、安全とけいれんの閾値を上げるために抗けいれん剤の投与は継続する。
ECT では特有の重大な生理的変化が生じるため、この治療に精通していない麻酔科とはECT は施行するべきではない。以前はECT の麻酔管理は単純なものと考えられていたが、事実は全く反対で、適切な文献を丁寧に読むことが麻酔科にとって重要である。全身麻酔を受ける全ての患者で心電図モニターとパルスオキシメーターを使用することは、ASA で承認されている。ECT 治療中の心電図を記録するだけでなく、平常時やけいれんじの心電図を記録することが重要である。そして、適切に心電図を監視るために、ECT と独立して紙記録が可能な手術室内モニターが必要である。
全身麻酔の導入にはmethohexital やプロポフォール、サクシニルコリンを用いる。硫酸アトロピンやグリコピロニウムのような抗コリン作用薬は、副交感神経系を介した不整脈を抑えるために、長い間使用されてきた。しかし、抗コリン薬は心拍数と心負荷を増加させ、心血管系イベントのリスクになるめ、現在では使用されなくなり、徐脈の時にのみ使用される。
冠動脈疾患や高血圧の患者に対して頸静脈的に短時間作用型β遮断薬を使用することは、心負荷を軽減するのに有効である。これらの薬物は高血圧、頻脈、期外収縮、心筋虚血を改善し、適切な使用であれば、低血圧や徐脈になることは稀である。麻酔導入前にエスモロール100~200mgやラベタロール10~20mgの急速静注は通常は有効である。これらの薬物はうっ血性心不全を生じさせる可能性があるが、実際の報告はない。心活動を減弱させる2番目の方法としてECT15分前にニフェジピン10mgを舌下する方法がある。β遮断薬やカルシウム拮抗薬がすでに使われている患者や、降圧剤の追加が必要な患者におけるECT への反応性の高血圧には、ニトログリセリン0.5~3.0μg/kg/ 分の静注を用いる。もし静注を行う場合は、少なくとも最初の治療では動脈内血圧をモニターすべきである。
ECT 前の適切な高血圧治療は、通常ECT 中の反応性の高血圧を減少させる。アテノロール25~50mgの毎日の経口投与のようなβ遮断薬の維持投与によって、ECT 中の短時間作用型の降圧剤の投与は不要となる。
心疾患のある患者は、ECT 中に心血管系の合併症を生じる可能性が高い。ECT 時の伝導系の以上が20~80%の患者で見られるという報告があるが、通常は一過性である。持続的あるいは重篤な不整脈は時に治療を要し、不整脈の種類によって治療を選択する。上室性頻拍は一般的にカルシウム拮抗薬が最も良い。心室生期外収縮はリドカインの静注で速やかに安定する。多くの不整脈は、ECT 前に短時間作用型のβ遮断薬を静注することにより予防できる。
うっ血性心不全は酸素投与と頭部挙上で通常は治療できる。時にフロセミドとモルヒネが必要になることがあるが、ごく稀なことである。多くの患者は積極的な治療をしなくても10~15分で再び代償される。
心停止はECT の稀な合併症である。いくつかの患者は、ECT 刺激後に無収縮が現れ、8秒間続くことがあり、本当の心停止と間違われるかもしれない。発作閾値に達していない通電を受けた場合は特に危険である。なぜなら、通電によって生じる副交感神経系の興奮伝達は、けいれん発作そのものによって生じる交感神経系の興奮伝達によって拮抗されないため、重篤な徐脈や心不全に繋がる。
E
CT に関連した罹患率と死亡率に関するいくつかの大規模研究がある。最近行われた後方視的研究では、2279人の患者が対象となり、合計で17394回のECT が施行され、そのうち合併症が生じたのは24例であった。心血管系の合併症が大半で、そのうちのほとんどが不整脈であった。永久的な後遺症や、施行中または直後に死亡した症例はなかった。
片側刺激法と両側刺激法のどちらが良いかは、まだはっきりしておらず、どちらもいい点も悪い点もある。片側刺激法は両側刺激法に比べて認知機能障害は起こしにくいが、効果は劣っている(そのためより重篤な場合や、片側刺激法で改善がなかった場合は、両側刺激法が第一選択となる)。マサチューセッツ総合病院では、治療抵抗性の躁病の患者を除いた全患者に、まず片側刺激法を行なっている。約5%のうつ病患者が6~12回の片側刺激法に対して治療抵抗性を示すが、その場合は両側刺激法に切り替える。片側刺激法が有効でないのは、通電が閾値以下であるか、電極同士が近すぎることに関連している。したがって、片側法では電極をd’Elia 位置に設置し、閾値を50%以上超える通電を行うべきである。
アメリカでは短い波形の通電波形が一般的となってきている。以前は正弦波形一般的であったが、短い波形の方がより効果的に発作活動を誘発し、治療後の錯乱や健忘が少ない。選ばれた患者に対しては、非常に短い波形での片側刺激法は、効果を保ちながら認知機能への影響を最小限にすることができる。うつ病を軽減するのに、ECT は週に2回行うのと3回では効果は同じであると主張するいくつかの研究もあるが、スケジュールは大抵週に3回である。この治療スケジュールは、改善は緩徐で、記憶障害はより起こりにくい。Keller たちは、週に1回の頻度のECT では抗うつ効果が臨床的にほとんどないとしている。
ECT の治療効果には全身性けいれんが重要である。全身性けいれんを確認する簡便な方法は、腕や踵に血圧計のカフを巻き、サクシニルコリンを静注する前に、収縮期血圧よりも高い圧をかけておくことである。その時、同部位より抹消でけいれんが観察できる。片側刺激法では、刺激側と同側の上肢か下肢にカフを取り付ける。多くのECT には1チャンネル脳波モニターが付いているが、この機器では部分発作も同様に記録されてしまうので、全身性けいれんの信頼できる指標とはならない。臨床的な抗うつ効果と発作の閾値と間隔の間に確固たる関係性は未だ明らかではない。
ECT 後、患者を仰臥位のままにしてはならず、分泌物が吸引しやすい側に側臥位にしておくべきである。回復室の看護師が注意深く観察し、バイタルサインを定期的に計測し、経皮的酸素飽和度を測定する。20人に1人の割合で、典型的には若く健康な患者において、治療直後から、虚ろな視線と失見当識、自動症、焦燥感の強いせん妄を呈する患者がいるが、この臨床像は通常は遅発性の発作である。ミダゾラム2~5mg、ジアゼパム5~10mgの静注で直ちに消失する。
うつ病の治療に必要なECT の平均施行回数は一貫して6~12回と報告されているが、時には30回も必要になる患者もいる。通常は、通電1回につき1回の全身性けいれんを誘発する単通電を週3回の頻度で行う。施行あたり2回以上の通電により発作を誘発する多通電がより効果的であることは証明されていない。
副次的な効果
ECT は脳に器質的障害を起こすという証拠はないものの、認知機能に対しては重大な影響がある。ETC 後の混乱と見当識障害は多彩であるが、それには両側刺激、高頻度刺激、不十分な酸素化、発作の遷延化、高齢、現在の神経学的疾患が関係している。ECT 後の見当識障害は比較的頻繁に起こるが、長引いたり、せん妄に分類されるまでのより重篤な混乱状態を生じたりする可能性ある。そのようなECT 後せん妄は、より高齢で、神経学的疾患が基礎にある患者の方がより起こりやすい。
最も一般的な認知面での副作用は、新しい情報の再生困難(前向健忘)であるが、通常は最終施行から1 ヶ月以内に回復する。autobiography memoryimpairment はECT の結果生じる。客観的な評価では、記憶喪失は比較的短い期間(治療後6ヶ月以内)で見られるが、主観的な評価では、健忘症はさらに長い期間(治療後6ヶ月以上)続く。ECT 前の出来事の再生困難(逆向性健忘)はECT に近い出来事ほど強く、両側法では片側法よりも記憶障害が顕著になる。これは前向性・逆向性健忘でも、言語的・非言語的再生の両方において認められる。記憶障害を最小限にする方法は、短い波形による片側法である。
ECT 後に重篤な器質性脳症候群を呈することは滅多にないが、生じた場合はECT を中断しなければならない。ECT が原因であれば、通常は48時間以内に改善する。しかし、中断後むしろ重症化した時は、ECT 以外に原因がある可能性があるので、十分な神経学的検査が必要となる。
維持療法
ECT により寛解した後の再発率は、維持的薬物療法を行わなかった場合、12ヶ月後で50%に達する。三環系抗うつ薬に十分な効果があるとした研究はほとんどない。MAO 阻害薬、リチウム、ブプロピオン、フルオキセチンを服用している患者では、より長く寛解状態が維持された。一般的に、維持的ECTは維持的薬物療法と比較して、有効で、安全で、費用も安く済む。また再発率や再入院率にも大きな効果がある。最近行われた、大規模な無作為化試験では、継続したECT 療法と、ノルトリプチンとリチウムの併用療法では、6ヶ月での効果はほとんど同じであったが、薬物療法の患者では、半分以上で再発や、医療の中断を経験していた。
要約
近年、総合病院精神科における電気痙攣療法の技術ははより洗練され、安全性が高まった。その結果、総合精神病院を受診するハイリスク患者の数が増加しているようだ。電気痙攣療法は特別な訓練と認定制が必要な専門分野とみなされるようになってきている。薬物抵抗性の患者に対しても電気痙攣療法は有効なことが多く、近い将来、電気痙攣療法が総合病院精神科の重要な治療となるだろう。